リスフラン靱帯損傷
リスフラン靱帯損傷
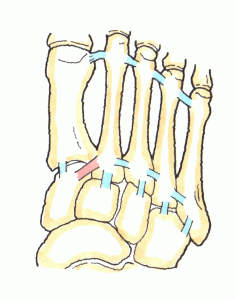
リスフラン関節部分を詳しく見ると,靱帯が,それぞれの骨をきっちりと締結しています。
オレンジ色の靭帯が,リスフラン靭帯です。
水色で囲んだ靭帯は,隣り合う骨どうしを互いに締結していますが,リスフラン靭帯だけは斜めに走行し,斜め下の第2中足骨と楔状骨(けつじょうこつ)を連結しています。

足の骨を横から見ると,リスフラン関節部分の頂点部は,足のアーチの頂点と一致しており,足部に体重がかかったときに,この関節がクッションの役目を果たしています。
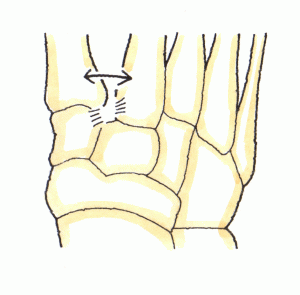
リスフラン靭帯が損傷すると,つなぎ止めていた骨同士の連結が無くなり,上図の矢印の様に骨の間の隙間が開くようになります。
このことを,中足・楔状骨間離開(ちゅうそく・きつじょうこつりかい)と言います。
つまり靭帯が切れて,骨どうしをつなぎ止めることができないので, リスフラン関節部分が不安定な状態になり,アーチ構造が崩れて,体重をかけたときに痛みを生じるのです。
リスフラン関節脱臼骨折・リスフラン靱帯損傷における後遺障害
<ケース>MRIで立証しても「とき、すでに遅し」が存在する?
30代前半の男性の例。
足の甲の部分を押さえると激痛が走り,歩行時の痛みが強い。
足の甲がやや腫れぼったく,第1中足骨近位端部を軽く押すと痛みを訴えるが,激痛ではない。
事故後,8ヶ月を経過して撮影されたMRIで,僅かな中足・楔状骨間離開が認められた。
ほぼリスフラン靱帯損傷の状況だが,診断書の傷病名は,「足関節の打撲・捻挫」。
保険会社から打ち切りを打診され,念のために受診した医大系の病院でMRI撮影を受け,靱帯損傷の可能性を指摘されたが,事前認定の結果は非該当だった。
<解説>
受傷直後にリスフラン靱帯損傷と診断されていることが理想ですが,これは,主治医の診断力次第であり,被害者がコントロールできることではありません。
傷病名の診断がなくても,足の甲部分に激痛と歩行時の痛みなどの自覚症状があり,それらがカルテに記載されていれば,その後に傷病名が確定しても,後遺障害の可能性が見えてきます。
後遺障害は獲得できるか?
リスフラン関節の脱臼骨折のトピックでは,一般的には,ほとんど後遺障害を残すことはないとご説明しました。
それはあくまでも一般論です。交通事故で加わる外力はスポーツの比ではなく,さらに被害者の身体能力もそれほど鍛えられていないことがほとんどです。
痛みを残していれば3DCTで骨癒合状況を,靱帯損傷はMRIで立証することにより,14級9号,12級13号を獲得した例があります。
関連記事はこちら
- ACL前十字靱帯損傷
- LCL外側々副靭帯損傷
- MCL内側々副靱帯損傷
- PCL後十字靱帯損傷
- PLS膝関節後外側支持機構の損傷
- SLAP損傷=上方肩関節唇損傷
- アキレス腱断裂
- アキレス腱滑液包炎
- ステム周囲骨折
- モートン病
- 下腿のコンパートメント症候群
- 下腿骨の切断、足趾の切断
- 二分靱帯(にぶんじんたい)損傷
- 仙髄神経麻痺(せんずいしんけいまひ)
- 半月板損傷
- 右肘内側々副靱帯損傷
- 右腓骨筋腱周囲炎・右腓骨筋腱炎
- 右腓骨遠位端線損傷
- 坐骨・腓骨・脛骨神経麻痺
- 坐骨神経麻痺
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 外傷性内反足
- 外傷性骨化性筋炎
- 外傷性骨化性筋炎
- 有痛性外脛骨
- 浅腓骨神経麻痺
- 深腓骨神経麻痺=前足根管症候群
- 肉離れ、筋違いと捻挫について
- 股関節の仕組み
- 股関節中心性脱臼
- 股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)
- 脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目
- 脛骨神経麻痺
- 腓腹筋断裂 肉離れ
- 腓骨神経麻痺
- 膝窩動脈損傷
- 膝蓋前滑液包炎
- 膝蓋骨脱臼
- 膝関節の仕組み
- 複合靭帯損傷
- 足の構造と仕組み
- 足の構造と仕組み
- 足底腱膜断裂
- 足底腱膜炎
- 足根洞症候群
- 足根管症候群
- 足根骨の構造
- 足関節に伴う靱帯損傷のまとめ
- 足関節の構造と仕組み
- 足関節不安定症
- 足関節果部脱臼骨折、コットン骨折
- 足関節離断性骨軟骨炎
- 距骨々軟骨損傷
- 骨盤の仕組み
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
【受付時間】 10:00-20:00

