脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目
脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目
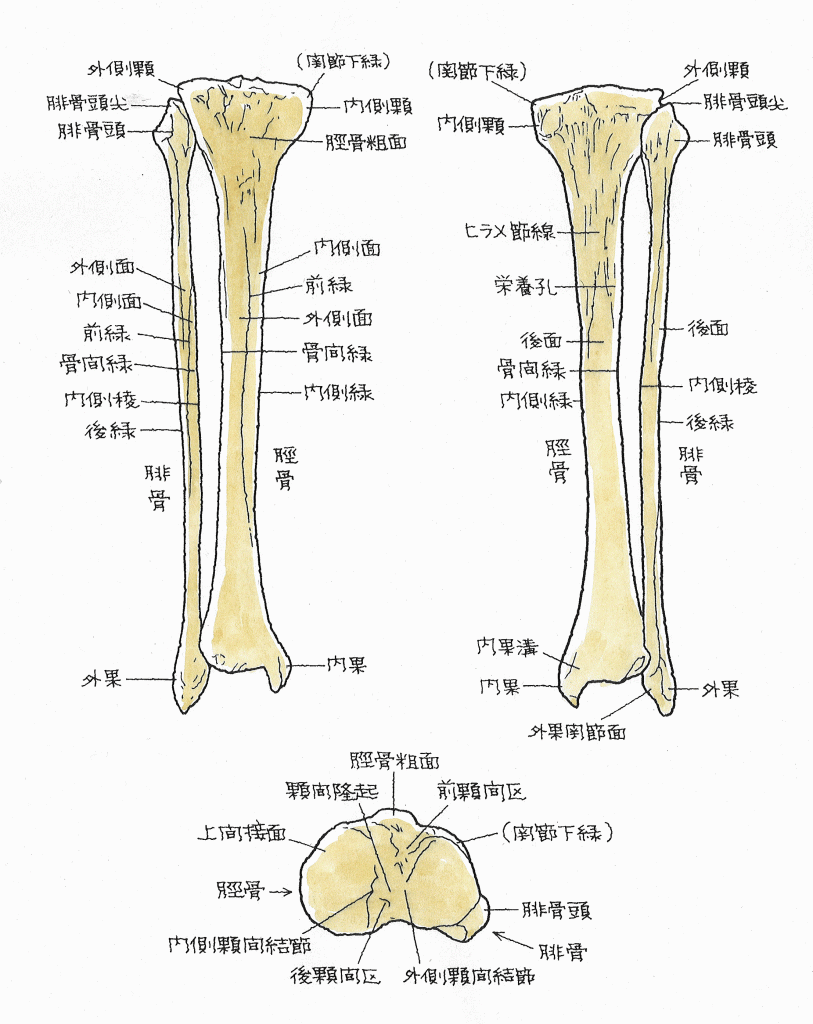
脛骨とは膝と足首の間にあり,すねを形成する太い骨のことで,下腿の前面内側に位置し,腓骨と対になって下腿を支えています。
脛骨は大腿骨に続いて,二番目に長い骨で,膝から上の全体重を支える役目を果たしています。
すねをぶつけて飛び上がるほど痛いところ,いわゆる弁慶の泣き所は,脛骨です。
交通事故においては,膝関節と連結しているため,脛骨を骨折すると,関節内の構造体である半月板や靭帯損傷を合併し,重症化することが多いのです。
膝のお皿の下を外側に触っていくとボコッと出ている骨があります。
その出っ張りと,足首の外くるぶしを結んでいるのが腓骨です。
脛・腓骨々幹部骨折では,腓骨の一部を骨採取し,脛骨の骨折部に移植することも行われており,腓骨は骨折しても日常生活に影響しないと思われていますが,腓骨は,実は,膝や足首の痛み,足の疲労に大きく関係しています。

腓骨々幹部骨折のXP画像です。
転位が大きく,AOプレートで内固定されています。
腓骨の役割は,2つあるのですが,まず第1は,歩行時の衝撃の吸収です。
人は地面からの反発力を吸収しながら歩き,走っています。
一歩一歩ごとのショックアブソーバー機能は,腓骨の働きによるものです。
もう1つの役割は,腓骨の存在により,その下の足関節を,さまざまな方向に動かせることです。
サッカーの絶妙なシュートやパス,あるいはドリブルなどは,下腿骨が2本あることにより,足首が自在に動くことではじめて可能になるのです。
最近,腓骨体重によるO脚が問題提起されています。
太さが脛骨の4分の1に過ぎない腓骨に頼り,足の外側で体重を支えている人が増えているのです。
体重は太い骨の脛骨に掛けるべきですが,無意識に腓骨に体重を掛ける人が増えているのです。
脛骨体重では,かかとに体重が乗り安定しますが,腓骨体重では,かかとに体重が上手く乗らず,小指側体重になり,バランスを外側に崩しやすい,膝痛,足首の痛み,ふくらはぎの疲れ,O脚になりやすくなるのです。どの骨に体重をかけるかで 足の負担が変わるので,重要なポイントです。
腓骨は転位しやすい骨であり,腓骨体重,足組み,草むしりなど膝を曲げる姿勢などを長時間続けると,腓骨は,やや外側に転位していきます。
腓骨は腓骨神経を圧迫しやすい為,腓骨のずれが大きくなると膝下の外側から足の甲にかけてのしびれや感覚異常,足首や足指を上げることができない,つまずきやすくなる等の症状が出現します。
腓骨の転位は,痛みだけでなく,しびれにも関係してくるのです。
関連記事はこちら
- ACL前十字靱帯損傷
- LCL外側々副靭帯損傷
- MCL内側々副靱帯損傷
- PCL後十字靱帯損傷
- PLS膝関節後外側支持機構の損傷
- SLAP損傷=上方肩関節唇損傷
- アキレス腱断裂
- アキレス腱滑液包炎
- ステム周囲骨折
- モートン病
- リスフラン靱帯損傷
- 下腿のコンパートメント症候群
- 下腿骨の切断、足趾の切断
- 二分靱帯(にぶんじんたい)損傷
- 仙髄神経麻痺(せんずいしんけいまひ)
- 半月板損傷
- 右肘内側々副靱帯損傷
- 右腓骨筋腱周囲炎・右腓骨筋腱炎
- 右腓骨遠位端線損傷
- 坐骨・腓骨・脛骨神経麻痺
- 坐骨神経麻痺
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 外傷性内反足
- 外傷性骨化性筋炎
- 外傷性骨化性筋炎
- 有痛性外脛骨
- 浅腓骨神経麻痺
- 深腓骨神経麻痺=前足根管症候群
- 肉離れ、筋違いと捻挫について
- 股関節の仕組み
- 股関節中心性脱臼
- 股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)
- 脛骨神経麻痺
- 腓腹筋断裂 肉離れ
- 腓骨神経麻痺
- 膝窩動脈損傷
- 膝蓋前滑液包炎
- 膝蓋骨脱臼
- 膝関節の仕組み
- 複合靭帯損傷
- 足の構造と仕組み
- 足の構造と仕組み
- 足底腱膜断裂
- 足底腱膜炎
- 足根洞症候群
- 足根管症候群
- 足根骨の構造
- 足関節に伴う靱帯損傷のまとめ
- 足関節の構造と仕組み
- 足関節不安定症
- 足関節果部脱臼骨折、コットン骨折
- 足関節離断性骨軟骨炎
- 距骨々軟骨損傷
- 骨盤の仕組み
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
【受付時間】 10:00-20:00

