膝蓋骨脱臼
膝蓋骨脱臼
膝蓋骨脱臼とは,膝のお皿が,膝の正面の本来の位置から外れることで,膝の構造・形態的特徴から,ほとんどは大腿骨に対して外側に脱臼しています。
膝蓋骨は膝の輪切り図では,大腿骨正面の溝にはまるような位置にあります。
膝蓋骨が溝を乗り越えて外れることを脱臼,乗り越えてはいないが,ずれることを亜脱臼と呼びます。
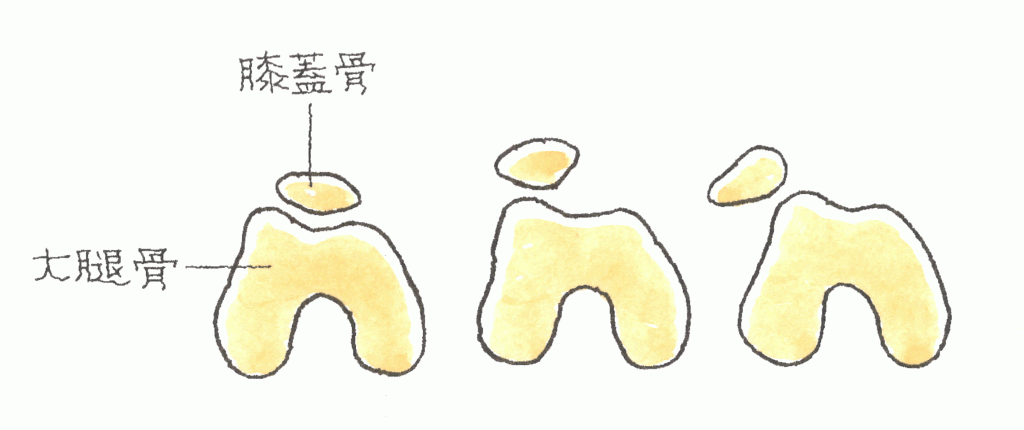
左から,正常・亜脱臼・脱臼のイメージ図
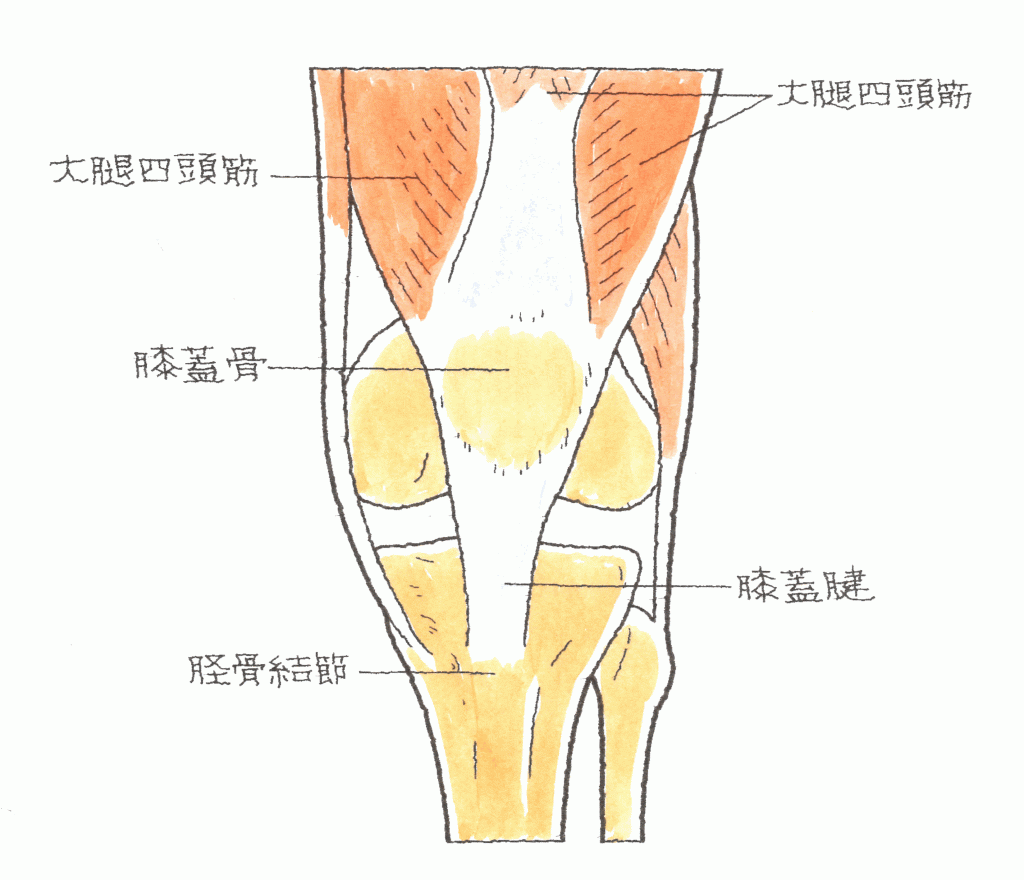
膝蓋骨は,太ももの側では大腿四頭筋という強い筋肉に,すねの側では膝蓋腱という線維につながり脛骨に連結しています。膝蓋骨は曲がった膝を伸ばすときに,滑車のような役目で大腿四頭筋の筋力を脛骨に連結しています。膝蓋骨は曲がった膝を伸ばすときに,滑車のような役目で大腿四頭筋の筋力を脛骨側に伝えるのをサポートしています。
膝蓋骨脱臼は10代の若い女性に多く発症し,スポーツ活動中などに起こります。
膝蓋骨脱臼はジャンプの着地などで筋肉が強く収縮したときや,膝が伸びた状態で急に脛骨をねじるような力が加わったとき,膝蓋骨を打撲したときに発症していますが,元々膝蓋骨が脱臼しやすい身体的条件,膝蓋骨に向き合う大腿骨の溝が浅い,膝蓋骨の形成不全,膝蓋腱の付着部が外側に偏位しているなど,遺伝的要因のある人に起こりやすいと言われています。
脱臼を発症しても,多数例で膝蓋骨は病院に搬送される前に,元の位置に戻ります。
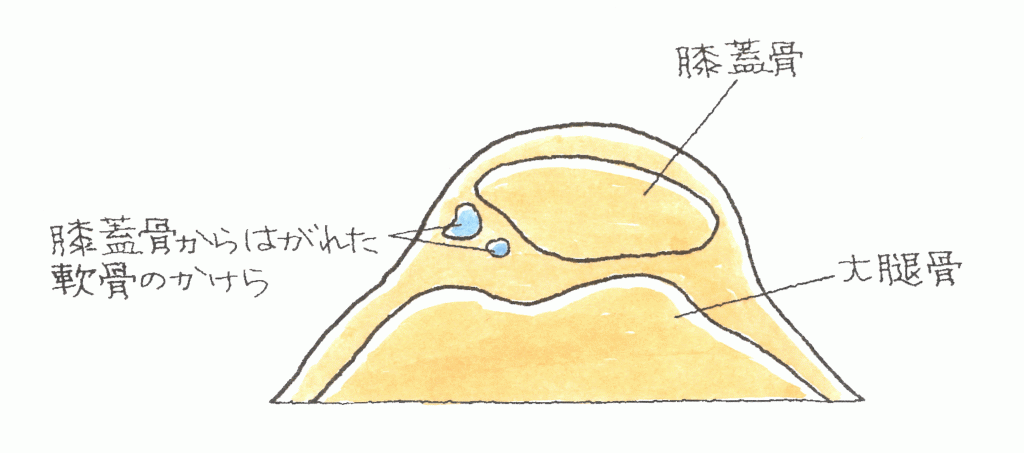
脱臼に伴い,50%の被害者に,軟骨や骨の損傷が起こると言われますが,その程度によっては早期に手術が必要になることもあります。
手術が必要ないと判断されたときは,まず膝を装具,サポーターなどで固定することになります。
痛みや関節の腫れが改善した段階では,徐々に体重をかけて歩き,膝を動かすようにします。
膝蓋骨脱臼の20~50%に再脱臼が起こると報告されています。
再脱臼をしなくても50%以上に,痛みや膝の不安定感などの症状が残ります。
再脱臼を予防するための治療として,リハビリや運動用の装具による治療を行います。
リハビリでは,膝蓋骨が外側にずれてしまうことを防ぐように膝蓋骨の内側につく筋肉を強化,膝蓋骨を外側に引き寄せる筋肉や靭帯をストレッチで柔軟性を高める,脱臼を誘発するような姿勢や動作を回避するような運動を繰り返して練習します。
運動用の装具は,膝蓋骨が外側にずれるのを防ぐ構造物のついたものを使用します。
装具は脱臼後の早い時期に日常生活で使用,その後の一定期間はスポーツなどで使用します。
関連記事はこちら
- ACL前十字靱帯損傷
- LCL外側々副靭帯損傷
- MCL内側々副靱帯損傷
- PCL後十字靱帯損傷
- PLS膝関節後外側支持機構の損傷
- SLAP損傷=上方肩関節唇損傷
- アキレス腱断裂
- アキレス腱滑液包炎
- ステム周囲骨折
- モートン病
- リスフラン靱帯損傷
- 下腿のコンパートメント症候群
- 下腿骨の切断、足趾の切断
- 二分靱帯(にぶんじんたい)損傷
- 仙髄神経麻痺(せんずいしんけいまひ)
- 半月板損傷
- 右肘内側々副靱帯損傷
- 右腓骨筋腱周囲炎・右腓骨筋腱炎
- 右腓骨遠位端線損傷
- 坐骨・腓骨・脛骨神経麻痺
- 坐骨神経麻痺
- 変形性股関節症
- 変形性膝関節症
- 外傷性内反足
- 外傷性骨化性筋炎
- 外傷性骨化性筋炎
- 有痛性外脛骨
- 浅腓骨神経麻痺
- 深腓骨神経麻痺=前足根管症候群
- 肉離れ、筋違いと捻挫について
- 股関節の仕組み
- 股関節中心性脱臼
- 股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)
- 脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目
- 脛骨神経麻痺
- 腓腹筋断裂 肉離れ
- 腓骨神経麻痺
- 膝窩動脈損傷
- 膝蓋前滑液包炎
- 膝関節の仕組み
- 複合靭帯損傷
- 足の構造と仕組み
- 足の構造と仕組み
- 足底腱膜断裂
- 足底腱膜炎
- 足根洞症候群
- 足根管症候群
- 足根骨の構造
- 足関節に伴う靱帯損傷のまとめ
- 足関節の構造と仕組み
- 足関節不安定症
- 足関節果部脱臼骨折、コットン骨折
- 足関節離断性骨軟骨炎
- 距骨々軟骨損傷
- 骨盤の仕組み
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
【受付時間】 10:00-20:00

