膵臓損傷2
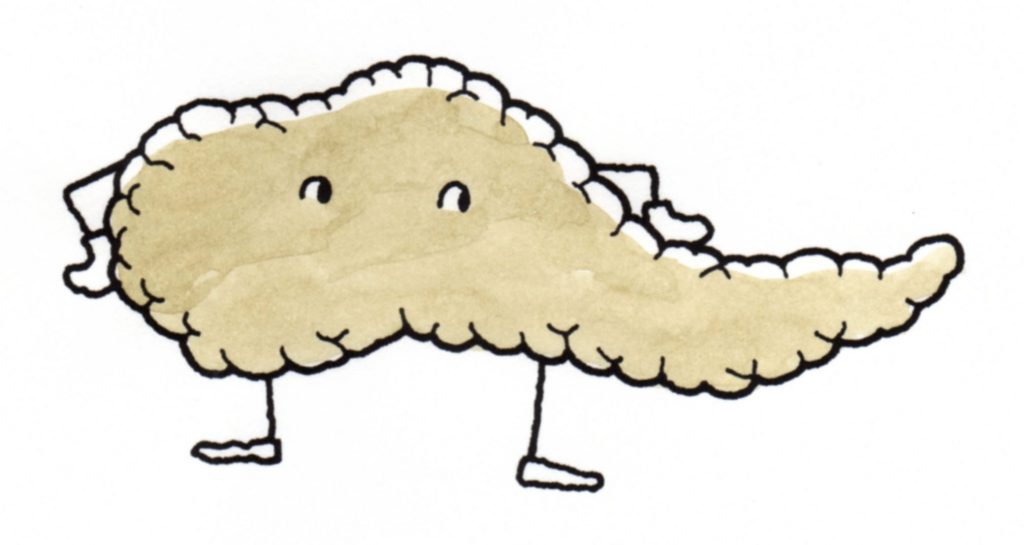
膵臓の損傷における後遺障害のポイント
1)膵臓が切除されると、外分泌機能が障害され、低下することが通常とされています。
膵臓の部分切除がなされており、上腹部痛、脂肪便および頻回の下痢など、
外分泌機能の低下に起因する症状が認められるときは、労務の遂行に相当程度の支障が
あるものとして11級10号が認定されています。
※脂肪便とは、消化されない脂肪が便と一緒にドロドロの状態で排出されるもので、
常食摂取で1日の糞便中、脂肪が6g以上であるものを言います。
2)膵臓周囲のドレナージが実施されるも、部分切除が行われていないときは、
①CT、MRI画像で、膵臓の損傷が確認できること、
②上腹部痛、脂肪便および頻回の下痢など、外分泌機能の低下に起因する症状が認められ、
かつ、PFD試験で70%未満または、糞便中キモトリプシン活性で24U/g未満の異常低値を
示していること、
上記の2つの要件を満たしているときは、11級10号が認められています。
医学的に、外分泌機能の低下が認められるときは、血液検査で、血清アミラーゼまたは、
血清エラスターゼの異常低値を認めれば、11級10号が認定されています。
※PFD試験=膵臓の外分泌機能検査
膵臓は2つの異なる働きをしており、1つは、食物の消化に必要な消化酵素、
炭水化物を分解するアミラーゼ、蛋白を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなどを
含んだ膵液を12指腸に分泌する外分泌機能です。2つ目の作用は、血糖を下げるインスリンと
血糖を上げるグルカゴンを血液中へ分泌して、血糖を調節する内分泌機能です。
PFDは、膵臓の外分泌機能検査法の1つです。
薬剤を服用後、6時間尿を採取する方法ですので、体に負担はかかりません。
膵臓の外分泌機能が低下するような病気で、異常値、低値を示します。
この薬剤は小腸から吸収され、肝で化学変化を受けた後、腎から排泄されます。
したがって、膵外分泌機能の低下以外に、小腸における吸収低下のある場合、
肝機能や腎機能低下のある場合にも、尿中の値は低下します。
早朝空腹時排尿後に、BT-PABAというPFD試薬500mgを水200mLとともに服用します。
開始6時間後の尿を全部集め、尿量を測ります。
採取した尿の一部を使って、尿中PABA濃度を比色測定し、尿中PABA排泄率(%)を
計算します。正常値は71%以上です。
※糞便中キモトリプシン活性測定試験
便の一部を採取して、その中に含まれる膵酵素の1つであるキモトリプシンの働きを調べる検査です。
厚生労働省の診断基準では、外分泌機能検査としてPFD試験と便中キモトリプシン活性測定を
あげており、2つの低下を、同時に2回以上認めることを求めています。
基準範囲は13.2U/gです。
しかし、ネットでは、試薬が作られなくなり、現在は行われていないと、複数掲載されています。
※アミラーゼ、エラスターゼ
アミラーゼとは、膵臓から分泌される消化酵素の1つで、以前はジアスターゼと呼ばれていました。
分泌されたアミラーゼは、血液中に流出し、血中に含まれますが、この血中に含まれる
アミラーゼが血清アミラーゼです。
アミラーゼの基準値は、40~132 lU/lで、低下が認められるのは39以下です。
エラスターゼは、動脈壁や筋肉の腱を構成するエラスチンという成分を分解する酵素のことで、
膵臓、白血球、血小板、大動脈などに存在しています。
エラスターゼには1と2がありますが、血中にはエラスターゼ1が圧倒的に多く、
こちらで検査が行われています。血液を採取し、遠心分離機で分離した血清部分を分析器で
測定します。
エラスターゼ1の基準値は、72~432ng/dlで、低下が認められるのは71以下です。
3)次は、膵臓の内分泌機能の低下です。
これは、経口糖負荷検査により判定することになります。
①正常型 膵損傷後に障害を残さないものであって、
空腹時血糖値<110mg/dlかつ75g OGTT 2時間値<140mg/dlであるもの
②境界型 膵損傷後に軽微な耐糖能異常を残すもの
空腹時血糖値≧110mg/dlまたは75g OGTT 2時間値≧140mg/dlであって、
糖尿病型に該当しないもの
③糖尿病型 膵損傷後に高度な耐糖能異常を残すもの
空腹時血糖≧126mg/dlまたは75g OGTT 2時間値≧200mg/dlのいずれかの要件を満たすもの。
要件を満たすとは、異なる日に行った検査により2回以上確認されたことを要します。
内分泌機能の障害による後遺障害の認定基準は、
①経口糖負荷検査で境界型または糖尿病型と判断されること、
インスリン投与を必要とする者は除かれています。
②インスリン異常低値を示すこと、
インスリン異常低値とは、空腹時血漿中のC-ペプチド=CPRが0.5ng/ml以下であるものを言います。
③2型糖尿病に該当しないこと、
上記3つの要件を満たせば、内分泌機能の障害として、11級10号が認定されています。
※経口糖負荷検査
空腹時血糖値および75gOGTTによる判定区分と判定基準
| 血糖測定時間 | 判定区分 | |
| 空腹時 | 負荷後2時間 | |
| 126mg/dl以上 | 200mg/dl以上 | 糖尿病型 |
| 糖尿病型にも正常型にも属さないもの | 境界型 | |
| 110mg/dl未満 | 140mg/dl未満 | 正常型 |
75gOGTTの手順は、
①前夜21:00以後絶食で、朝まで空腹のまま来院させる。
②空腹のまま採血し、血糖値を測定します。
③ブドウ糖75gを溶かした水を飲ませる。
④ブドウ糖を負荷した後、30分、1時間、2時間後に採血し、血糖値を測定します。
⑤糖尿病型、正常型、境界型のいずれかを判定します。
※2型糖尿病
1型糖尿病は、インスリンを作り出す膵臓=膵βベータ細胞が破壊・消失することで発症します。
2型糖尿病は、過食や運動不足などの生活習慣が発症に関係しています。
交通事故を原因として、2型糖尿病を発症することはありません。
したがって、2型糖尿病の治療の基本は、生活習慣改善のための食事療法や運動療法ですが、
1型糖尿病の治療は、インスリンを継続的に適切に補充することです。
4)外分泌機能と内分泌機能の両方に障害が認められるときは、
服することができる労務が相当な程度に制限されると考えられるところから、
9級11号が認定されています。
5)膵臓損傷では、膵臓の切除術が実施されることが一般的ですが、術後は、
腹部にドレーンが挿入され、膵液の漏出に対応しています。

膵液は、脂肪、蛋白、炭水化物を分解するための消化酵素を含んだ液です。
重症の膵液瘻では、多量の膵液漏出があり、電解質バランスの異常、代謝性アシドーシス、
蛋白喪失や局所の皮膚のただれ、びらんが生じ、膵液ドレナージと膵液漏出に伴う体液喪失に
対しては、補液、電解質を供給するなどの治療が必要となります。
つまり、このレベルでは、治療が必要であり、症状固定にすることはできません。
しかし、軽微な膵液瘻で、治療の必要性はないものの、難治性のものが存在しているのです。
これが続くと、瘻孔から漏れ出た膵液により、皮膚のただれ、びらんを発症します。
軽度な膵液瘻により、皮膚にただれ、びらんがあり、痛みが生じているときは、
局部の神経症状として12級13号、14級9号のいずれかが認定されています。
※代謝性アシドーシス
ヒトが生存していくには、体内の酸性とアルカリ性を、良いバランスに保たなければなりません。
これを、酸塩基平衡と呼ぶのですが、具体的には、ph=水素イオン濃度が7.4の状態です。
酸は、酸性、塩基は、アルカリ性、平衡は、バランスをとることなのです。
pHの数値が7.4以下となると、酸性に傾く=アシドーシス、以上では、
アルカリ性に傾く=アルカローシス状態となります。酸性の物質が体内に増えれば
アシドーシスとなるのですが、アルカリ性の物質を大量に喪失しても、酸性に傾きます。
ひどい下痢で、アルカリ性の腸消化液を大量に喪失すると、pHは酸性に傾く、
アシドーシス状態となり、皮膚は弱酸性、腸液はアルカリ性ですから、
下痢でお尻がヒリヒリするのです。
ヒリヒリは、ただれることですが、医学となると、びらんと難しく表現するのです。
6)膵臓全摘、糖尿病型でインスリンの継続的投与が必要なもの
未経験ですが、交通事故では、不可逆的損傷も予想され、上記はあり得ることです。
交通事故で肝臓が破裂し、修復が不能のときは死に至ります。
ところが、胆嚢や膵臓の破裂では、全摘術が行われているのです。
膵臓全摘で生存するには、インスリン注射を継続しなければなりません。
2006年7月、作家の吉村昭さんは、膵臓癌により79歳で亡くなりましたが、
同年の2月に膵臓全摘術を受け、全摘後は、4時間おきにインスリンの注射を続けました。
労災保険では、膵臓全摘、糖尿病型でインスリンの継続的投与が必要なもの治癒とすることは
適当でないと結論しています。
では、自動車保険では、どうでしょうか?
症状固定を先送りにすれば、本件交通事故の解決も、自動的に先送りとなります。
これを保険会社が認めるとも思いませんが、被害者としても、宙ぶらりんでは困ります。
やはり、示談書に付帯条項を盛り込み、いずれかの時点で、症状固定を決断することになります。
この場合の等級は、残存した後遺障害の労働能力におよぼす支障の程度を総合的に
判定することとされており、具体的な認定基準は、定められていません。
そして、膵臓全摘であっても、軽作業を前提に、就労復帰されている例もあります。
全摘だから、無条件で別表Ⅰの1級2号ではなく、個別に、支障を立証していかなければなりません。
関連記事はこちら
- 冠動脈の裂傷
- 副腎の損傷
- 外傷性の胃の破裂
- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)
- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア
- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)
- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)
- 大動脈について
- 大腸
- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂
- 小腸
- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)
- 尿崩症(にょうほうしょう)
- 尿管、膀胱、尿道
- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)
- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)
- 心肺停止(しんぱいていし)
- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)
- 心臓・弁の仕組み
- 心臓、弁の損傷
- 心臓の仕組み
- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)
- 横隔膜の仕組み
- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)
- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症
- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)
- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)
- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)
- 肝損傷 (かんそんしょう)
- 肺挫傷 (はいざしょう)
- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)
- 胃
- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)
- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について
- 脊髄損傷による排尿障害
- 脾臓(ひぞう)
- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂
- 腎臓
- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア
- 腹膜・腸間膜の障害
- 腹部臓器の外傷
- 膀胱の外傷
- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)
- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)
- 食道の仕組み
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
【受付時間】 10:00-20:00

