大腸
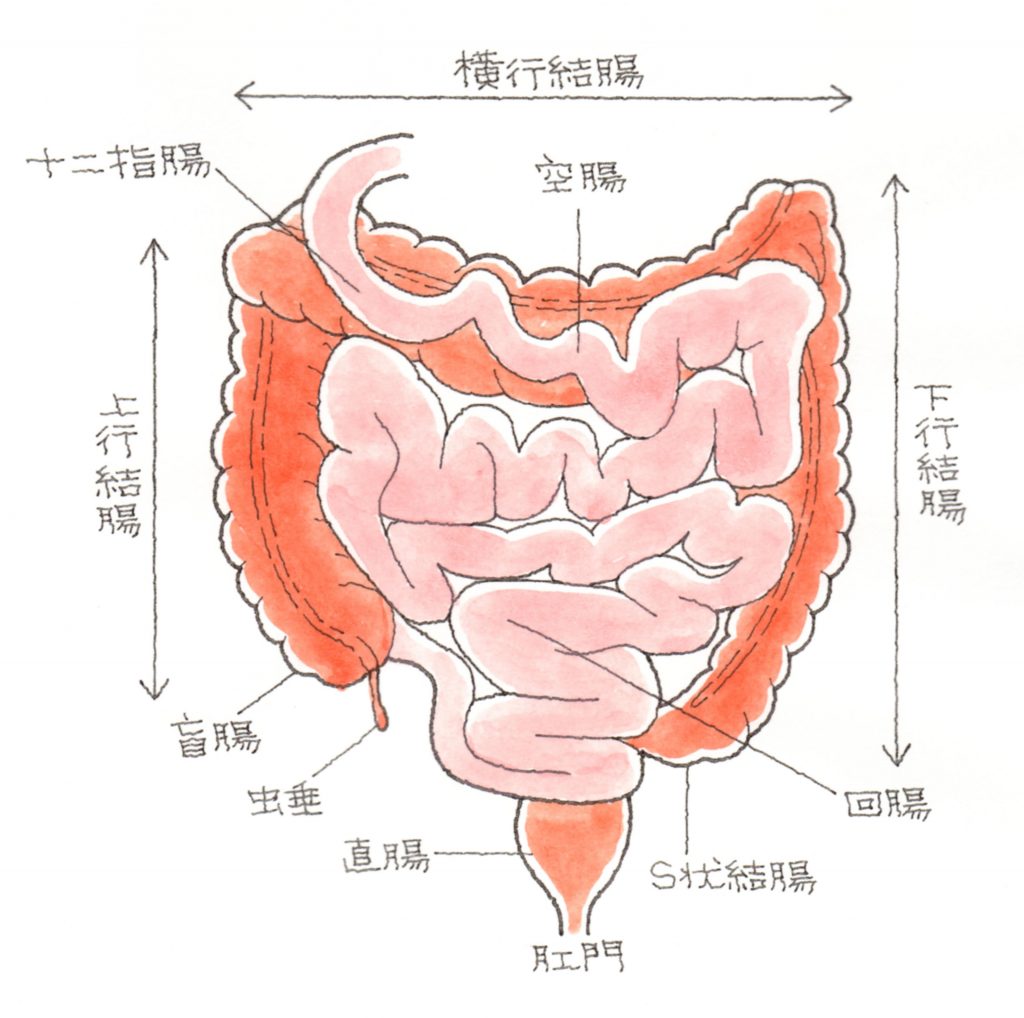
上のイラストのオレンジ色部分が大腸で、全長190cmの管腔臓器です。
盲腸からスタートし、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、最後に直腸で構成されています。
大腸は、糞便を固くするために、腸管の壁にある血管に、水分と塩類を吸収させる働きがあります。
また、糞便を滑らかにする粘液も分泌しています。
腸内の細菌を排泄し、細菌に対する防御も機構しています。
そして大腸筋肉の蠕動運動で、内容物を直腸に向かって移動させます。
大腸の運動は自律神経によって調節されていて、糞便は2種類の運動をしています。
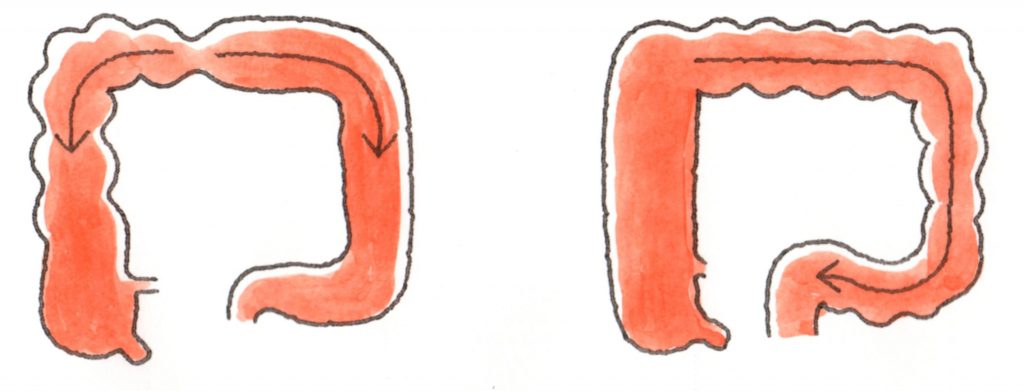
横行結腸部では、前に進む、元に戻る、シャトル運動を繰り返し、
大腸粘膜と内容物が長時間接触するようにしており、その運動で、水分と塩類の吸収を促進させます。
これを緊張波と呼んでいます。
もう1つは、横行結腸を空にするように、ゆっくりとした強い波が、上行結腸の上端で始まり、
糞便をS状結腸に進めて行きます。これを集団蠕動運動と呼んでいますが、
S状結腸は、排便まで糞便を貯留しています。つまり、ヒトの大腸は、
消化器官というよりも水分を回収する機能が高く、栄養吸収を完了した消化物を
便として整え、排出させる役目を担っています。
※排便のメカニズム
一定量の便が直腸に届くと、直腸粘膜の神経が感知し、大腸各部に信号を送り、
排便体制を整えるのですが、同時に、大脳にも情報伝達を行い、便意を生じさせるのです。
排便命令が脳から伝達されると、以下の大結腸運動が起こります。
大腸の横行結腸の開始部分から大きな収縮が起こり、中に貯まっている便を一気に、
下行結腸からS字結腸と直腸まで押し出すのです。
肛門を閉じている内・外括約筋は、便が漏れ出ないようにきっちり肛門を締めているのですが、
トイレに入り、排便姿勢をとると肛門が緩み、開くのです。
内括約筋が、先に反射的に緩み、外括約筋が意思にしたがって緩み、排便が行われているのです。
関連記事はこちら
- 冠動脈の裂傷
- 副腎の損傷
- 外傷性の胃の破裂
- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)
- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア
- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)
- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)
- 大動脈について
- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂
- 小腸
- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)
- 尿崩症(にょうほうしょう)
- 尿管、膀胱、尿道
- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)
- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)
- 心肺停止(しんぱいていし)
- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)
- 心臓・弁の仕組み
- 心臓、弁の損傷
- 心臓の仕組み
- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)
- 横隔膜の仕組み
- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)
- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症
- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)
- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)
- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)
- 肝損傷 (かんそんしょう)
- 肺挫傷 (はいざしょう)
- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)
- 胃
- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)
- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について
- 脊髄損傷による排尿障害
- 脾臓(ひぞう)
- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂
- 腎臓
- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア
- 腹膜・腸間膜の障害
- 腹部臓器の外傷
- 膀胱の外傷
- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)
- 膵臓損傷2
- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)
- 食道の仕組み
交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所
【受付時間】 10:00-20:00

